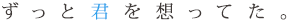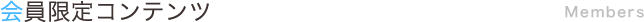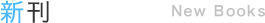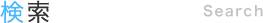月を食べて恋をする
恵多は掌にのせた真珠のピアスを、じっと見詰める。以前――まだ記憶を取り戻していない時期に、章介のジャケットのポケットから出てきたものだ。
この真珠のピアスだけではない。章介はよく女性物の香水の匂いを移して帰ってきた。
――三年もあれば、いろいろあって当たり前だよな。
むくむくと湧き起こってくる嫉妬心をなんとか鎮めようとしていると、ふいに章介の部屋のドアが開く音がした。恵多は慌てて、勉強机の抽斗にピアスを戻そうとして……取り落とした。
「なあ、ケータ」
ドアを開けた章介の足元へと、ピアスが弾み、転がっていく。
章介が怪訝そうにそれを拾い上げ、顔を曇らせた。
「このピアスは、誰のだ?」
咎める低い声で問われて、恵多は思わずムッとする。
「さーね」
そう返して勉強机に頬杖をついてプイと横を向くと、章介が荒い足取りで近づいてきた。そして華奢なピアスを恵多の前に指で摘んで突き出した。
「ケータ、まさか――」
オレンジ色がかった眸で、恵多は叔父を睨め上げた。
「まさか、じゃねぇよ。ショースケがヤった女のだろ。ショースケの服から出てきたんだから」
章介が瞬きをして、とたんに気まずそうな顔つきになる。それを見たとたん、三年ぶんの溜まった嫉妬が噴き出した。拳で机の天板を殴り、立ち上がる。
「ショースケはエロいし、仕方ないって頭ではわかってる。でもホント、嫌だったし。女の香水の匂いとかも、すげぇムカついた!」
章介がピアスを投げ捨て、恵多の肩をぐっと掴む。
「本当に違うんだ。お前と距離を置いておくために、俺が自分で買ったんだ。会社のロッカーにまとめて仕舞ったままになってるから、今度持って帰ってケータに見せるっ」
恵多が気圧されるぐらいの真剣さだ。
章介の黒い目は涙ぐんでしまっていた。
――……たぶん、本当なんだ。
ずっと好きだった人の表情だから、そうわかった。
嬉しい真相に涙ぐんでしまうのが気恥ずかしくて、恵多は章介の首に腕を巻きつけて、キスをした。
「エロいのは全部、俺だけにしてな」
一覧へ戻る
この真珠のピアスだけではない。章介はよく女性物の香水の匂いを移して帰ってきた。
――三年もあれば、いろいろあって当たり前だよな。
むくむくと湧き起こってくる嫉妬心をなんとか鎮めようとしていると、ふいに章介の部屋のドアが開く音がした。恵多は慌てて、勉強机の抽斗にピアスを戻そうとして……取り落とした。
「なあ、ケータ」
ドアを開けた章介の足元へと、ピアスが弾み、転がっていく。
章介が怪訝そうにそれを拾い上げ、顔を曇らせた。
「このピアスは、誰のだ?」
咎める低い声で問われて、恵多は思わずムッとする。
「さーね」
そう返して勉強机に頬杖をついてプイと横を向くと、章介が荒い足取りで近づいてきた。そして華奢なピアスを恵多の前に指で摘んで突き出した。
「ケータ、まさか――」
オレンジ色がかった眸で、恵多は叔父を睨め上げた。
「まさか、じゃねぇよ。ショースケがヤった女のだろ。ショースケの服から出てきたんだから」
章介が瞬きをして、とたんに気まずそうな顔つきになる。それを見たとたん、三年ぶんの溜まった嫉妬が噴き出した。拳で机の天板を殴り、立ち上がる。
「ショースケはエロいし、仕方ないって頭ではわかってる。でもホント、嫌だったし。女の香水の匂いとかも、すげぇムカついた!」
章介がピアスを投げ捨て、恵多の肩をぐっと掴む。
「本当に違うんだ。お前と距離を置いておくために、俺が自分で買ったんだ。会社のロッカーにまとめて仕舞ったままになってるから、今度持って帰ってケータに見せるっ」
恵多が気圧されるぐらいの真剣さだ。
章介の黒い目は涙ぐんでしまっていた。
――……たぶん、本当なんだ。
ずっと好きだった人の表情だから、そうわかった。
嬉しい真相に涙ぐんでしまうのが気恥ずかしくて、恵多は章介の首に腕を巻きつけて、キスをした。
「エロいのは全部、俺だけにしてな」