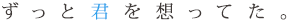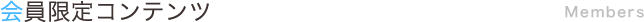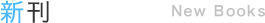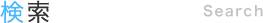一人上手は駆け引きが下手
「なんか、好きなの一個買ってやる」
カレシに連れてこられたアダルトショップで、いきなりこう言われたらどうふるまうのが正解だろうか。
桜岡歩は固まった。刑事である前田といい仲になって初めての、アダルトショップデートだ。
おそらく先週に給料が入ったらしく、ちょっといいお店で夕食をおごられた後だ。この後は歩の部屋で、買ったものも使ってきっとあれこれされるはずだ。
――大人ってエロい。
そう考えるが、期待に歩の全身は火照ってくる。もともと一人でアダルトグッズを使うのが大好きな歩だ。だが、それを使って前田にあれこれされると、とてつもなく身体が熱くなることを知った。そんな歩に、自ら自分を責めさせる道具を選ばせるなんて、前田はまったくたいしたどSだ。
――そういうところが、好きなんだけど。
だが、任されたからには選ばなければならない。弁護士を目指して司法試験受験対策真っ最中の歩は、ショーケースに眼鏡を向ける。
刑事の収入は安定してはいるだろうが、この場合に使って良い価格は一万円は超えないはずだ。かといって、安すぎるのはメンツを潰す。
だが、その値段で選べるものは無数にあった。
――今、不足しているものといえば、……ローターにつける、シリコンサックか……。
当て馬的な存在の男にあれこれされたおかげで、歩は余計な知恵をつけてしまった。
――だけど、あれは一個、数百円……。
必死になって考えを巡らす歩の前で、さっと前田は商品を手に取った。可愛いピンクのフェイクファーで覆われた手かせだ。
「可愛いから、これにしような」
あっさり言われる。もっと機能性と丈夫さを考慮した上で、価格に見合ったものを選びたい。それが、アダルトグッズ愛好家としてやってきた歩の矜持だ。
――だけど、……可愛い?
自分は前田にとって可愛い区分なのだろうか。
それをつけた自分の姿を想像してみただけで、似合わないよという思いと、愛されたいという欲望に全身が熱くなる。前田の希望に、今の自分が逆らえるはずがない。
「いいよ」
どんなたわいないものでも、前田と使うとすごくなる。これが恋の効力なのかもしれない。
一覧へ戻る
カレシに連れてこられたアダルトショップで、いきなりこう言われたらどうふるまうのが正解だろうか。
桜岡歩は固まった。刑事である前田といい仲になって初めての、アダルトショップデートだ。
おそらく先週に給料が入ったらしく、ちょっといいお店で夕食をおごられた後だ。この後は歩の部屋で、買ったものも使ってきっとあれこれされるはずだ。
――大人ってエロい。
そう考えるが、期待に歩の全身は火照ってくる。もともと一人でアダルトグッズを使うのが大好きな歩だ。だが、それを使って前田にあれこれされると、とてつもなく身体が熱くなることを知った。そんな歩に、自ら自分を責めさせる道具を選ばせるなんて、前田はまったくたいしたどSだ。
――そういうところが、好きなんだけど。
だが、任されたからには選ばなければならない。弁護士を目指して司法試験受験対策真っ最中の歩は、ショーケースに眼鏡を向ける。
刑事の収入は安定してはいるだろうが、この場合に使って良い価格は一万円は超えないはずだ。かといって、安すぎるのはメンツを潰す。
だが、その値段で選べるものは無数にあった。
――今、不足しているものといえば、……ローターにつける、シリコンサックか……。
当て馬的な存在の男にあれこれされたおかげで、歩は余計な知恵をつけてしまった。
――だけど、あれは一個、数百円……。
必死になって考えを巡らす歩の前で、さっと前田は商品を手に取った。可愛いピンクのフェイクファーで覆われた手かせだ。
「可愛いから、これにしような」
あっさり言われる。もっと機能性と丈夫さを考慮した上で、価格に見合ったものを選びたい。それが、アダルトグッズ愛好家としてやってきた歩の矜持だ。
――だけど、……可愛い?
自分は前田にとって可愛い区分なのだろうか。
それをつけた自分の姿を想像してみただけで、似合わないよという思いと、愛されたいという欲望に全身が熱くなる。前田の希望に、今の自分が逆らえるはずがない。
「いいよ」
どんなたわいないものでも、前田と使うとすごくなる。これが恋の効力なのかもしれない。