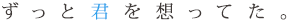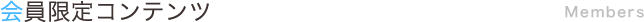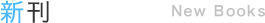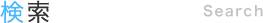ぼくだけの強面ヒーロー!
時計の針は四時を指していた。寝返りを打つ途中、枕元に夕べ置いたセロハンテープが見える。それから目の前にくる、七尾の寝顔。
意外と濃いまつ毛に気付くと、朝から変な気分になってきて、ユキはいそいそと起き上がった。落ち着かない。初めて七尾の下宿先に泊まったからだろうか。そわそわしながらテープを手に取った。薄汚れた二枚の画用紙の端を合わせてみる。しかし、ふわぁとあくびが零れ、あっと思うとテープはよれてしまっていた。
「あーっ」
思わず声が出た。眉を下げ、いびつな角度で繋がった画用紙を掲げる。見慣れない窓の向こう、薄紫色の空に思い出を透かすと、甲高い二人の笑い声が聞こえた。
「下手くそ」
「わっ!」
日に焼けた腕で布団の中に引きずり込まれ、ぐっと抱き寄せられる。思い出はひらりと舞って、少し先の畳に落ちてしまう。
「お前はテープを切る係。貼るのはおれ。決めただろ」
「あ、そうだった、ごめん」
鼻先でユキを見つめる七尾の目は少し赤い。濃いまつ毛につい目がいくからか、色っぽく見える。昨日より、ドキドキする。
「……添い寝でよくそこまで、ニヤついて赤面できるな」
ユキは両手で頬を庇ったが、この距離では無意味だろう。七尾は抱き寄せたユキを見つめ、眠いのか顔をしかめる。そして赤い目を潤ませて、急に黙った。……なにか怒っているらしい。なんでだろう。
「……え? あれ? テープのこと? 違う? あっ、えーと、起こしちゃってごめん?」
「起こされてない」
「えっ。じゃあさっき起きてたの? おれまたバカなこと……」
「お前はなにもしてない」
「は? なにそれ」
きょとんとするユキに、七尾は、赤い目を見開いた。
「いいか。夕べいきなりお前はおれに会いに来た。ド平日の、日付変わって寝ようとしてた時にだ。明後日まで叔父さんたち旅行でいないにしても、学校あるからダメだってのに、一緒に寝るって散々駄々こねておれに抱きついて、そのまま本当に寝た。なにもしないでな。どうだ、少しはまだ覚えてるか」
「お、覚えてるよちゃんと。だから、今度は我慢するって謝ったじゃん、それに電車が」
「そうじゃない」
「えっ? あ。じゃあ、わかった! 一緒に寝てくれてありがとう!」
「違うバカ!」
ああもう、と七尾は頭を掻きむしり、黒髪がユキの顔に触れる。汗の匂いがさっきより甘い。それでなるほど、彼は興奮しているのかと気付いた。
「七、……んぅっ!」
深く口づけられ、再び抱き寄せられて、息が詰まるほど密着する。押し付けられた七尾のそこはすでに熱く猛り、ユキの出した答えを肯定していた。蕩けていく頭で、彼の身体がこんなにも反応している理由を思うと、熱い痺れがそこ一点に集中する。
「ぁ……ん……」
「クソバカ。一睡もできなかった」
かすれた声で七尾は言った。口づけを解かれたユキは、赤い目で寝返りを打ち、唸る彼を想像する。ちょっと可愛かった。
「そっ、それってさ……、おれとくっついて、ドキドキしてくれたってことだよね?」
「……その言い方はやめろ」
「でも、わっ!」
ばさりと布団を剥がされた。
七尾は見せつけるように、寝間着の上を脱ぐ。鍛え抜かれた身体が朝焼けに照らされて、ユキは溜息を零す。こんなにもしなやかな流線を、内から滲み出る力強さを、いつか自分の手で描くことが、形にすることができるのだろうか。
「なにぼさっとしてる。……脱げ」
低い声はまたかすれている。ユキは頷いて起き上がり、言われるがままワンピースになっている借り物のTシャツを脱ぐ。七尾が黙っているので、靴下も脱いでみるが、彼は口を閉じたままだ。
「え、まだ脱ぐの」
「お前はついに、自分で下着も脱げなくなったのか」
「そっ、そうじゃ、ないけど……」
七尾の裸は見惚れてしまってドキドキするが、男同士だし、自分のを見られるのはあまり気にならない。……ただ。
朝焼けが、布団に膝をつき向かい合う二人を照らす。熱い顔を隠すものはなにもない。子供のようなユキの手足も、――勃ち上がっているそこも、すべてが茜色の光の下に曝け出された。
「ずいぶん勃ってるな」
「あ、朝だからっ!」
子供の頃にはなかった「男」の部分を見られると、条件反射でいたたまれなくなってしまう。七尾はちゃんと、どんなユキでも好きだと言ってくれたのに。
「タ、タケちゃんだって、人のこと……、あ!」
七尾はユキの腕を掴んで引き、空いた手でいきなりそこを握る。かくんと腰を落とすと、そのまま組み敷かれた。
「待っ……!」
ひゅっと細い息が零れる。七尾は赤い目を細めてユキを見下ろし、口の端を上げる。
「もう待った」
低く短く言われてユキは悟った。……こうなった時の七尾はやばい。
「あっ、――あ! あっ、あっ、ああッ」
言葉はない。耳に差し込まれた舌と、ぬるつき始めたそこが、淫靡な音を立てユキの背をしならせる。
「はぁ、あぁ……」
仕留められた獲物のように首筋を噛まれ、息を詰まらせる。わずかな痛みと、滲んで広がる熱に震えながら、声にならない声を上げてユキは達した。
「……ぁ……ッ」
「……早いんだよ、だから」
七尾が顔を上げた。赤い目が、まだ足りないと言うように細まる。大人の七尾の顔だ。底の知れない淫らな予感に、ユキはぞくりとする。
「お前このまえ、何回いったっけか」
余韻にひくつくユキの身体をほぐすように仰向けにして、七尾は薄く笑う。
「試してみるか」
「……え……、な……に」
「大丈夫だ」
七尾の笑みは、すぐに見えなくなった。ユキが身体を反らし叫んだからだ。だって七尾が、さっき出したもので汚れたままの、まだ勃ったユキのそこを、舌で――……。
「だ……! いやっ、いやっ、ああ……っあっ!」
七尾に食べられていく。ぬるりとすべて呑み込まれて、ユキは首を振った。震える手で七尾の髪を引く。
「だ……めぇ……ッ! あッ、だ、おねが……ッ」
今すぐやめさせたいのに、一番気持ちいい先端を吸われ、そこに舌をねじ込まれると、頭が真っ白になってしまう。むしろ欲しがるように、自然と腰を突き出す自分に気付き、涙が零れた。
「やめ……、ひっ、やだ……、や、ひっ」
快感か羞恥か、それとも嫌悪か。ごちゃまぜの涙が頬を伝い、すぐそこまで迫った欲求に、ユキはしゃくりあげた。こうなったら止められないとわかっている。何度も何度も、七尾を思い浮かべて自分でした時に、嫌というほど思い知らされている。
「……で、……ちゃうぅ……ッ、……はっ……な……」
言葉を紡ぐ余裕もなく、ユキはただ泣いた。もうだめだ。最悪だ。大好きな七尾の口に汚いものを注ぎ込むのを想像して、びくびくと足を引き攣らせながら嗚咽を零した。
すると、ゆっくりと七尾の口が離れる。ユキがほっとするのも束の間、そこから顔を上げた彼は、とんでもないことを要求した。
「飲ませろ」
七尾の目は本気だ。意味がわからない。ユキは首を振り腰を引くが、身体ごと抱き上げられ、引き戻される。
「お、おねがい。ほ、ほかのことっ、なんでも、するから……」
「お前は何度か、ここでおれのを飲んだ」
「んん……っ」
ぬめった指で後孔をゆるゆるといじられ、びくんとそこが脈打つ。今ここで出せればと思うのに、根元をきゅっと握られてしまう。
「あッ、――ッ!」
「おれには、よこさない気か」
「な……っ、なんでっ、だって、きっ、汚いじゃんか!」
「汚くない」
「ひ……、う……んっ」
変わらない表情で短くそう言い、七尾はユキの根元を握ったまま、空いたほうの手を滑らせ、静かに指を埋めた。そして内側から絞り出すように、一気に追い立てる。
「なら一度でいい」
「あッ、ああぁッ」
「――ユキの、全部が欲しい」
薄い唇にそこを強く吸われ、ユキは叫んだ。根元を握られているから出せない。違う。出しちゃいけない。どうしたいのかわからない。
――七尾はユキのを飲むと、興奮するんだろうか。……ユキが七尾を全部呑み込む時、すごく幸せに思うのと同じように?
「ひぁ、――あッ、あぁ、ああぁ……っ」
思った瞬間、根元から七尾の手が離れ、ユキは射精した。
そこが脈打つのに合わせて、彼の喉が鳴る。なにもかも全部飲み込まれて、……混ざり合って、七尾の一部になってゆく。そう思うと、なぜか胸の奥が熱くなって、温かい涙が頬に一筋流れた。
「ユキ」
七尾は身体を起こして、気を使った声を出す。ユキの身体はまだ余韻でひくついていた。出してからずっと、胸にしみこんでくるこの気持ちの名前を知らない。だから七尾の首に縋りつく。宥めるように髪を撫でられた。
「もう大丈夫だ。もうしない」
「……や、おれも……、なんか、大丈夫……、かも……」
二人同時に顔を上げる。七尾はふっと眉を下げた。
「なんなんだバカ。だったらなんで嫌々言った」
ぎゅっと抱き寄せられて、その手がわずかに震えているのに気付き、息が詰まる。
「ご、ごめんっ、……はじめて、で……」
こんなに温かくて泣きそうな気持ちがあるなんて、知らなかった。
七尾はへの字の口をユキに押し付ける。反射的に口を開くユキの、好きなところを何度もなぞってくれる。そしてまた、ゆるゆるとユキの中心を握り始める。
「ん……。ねえ、おれ……は、もう、いいよ……、タケちゃんのほう……」
「お前さっき、なんでもするって言ったな」
「へ?」
「バカは本当、すぐ忘れるから困る」
低く七尾は笑って、ユキの耳を舐めながら囁いた。
「何回いけるか、試すって言っただろ」
返す言葉を見つける前に、全身を貪られて、吐息さえ唇で奪われて、蕩ける頭も身体もばらばらになってゆく。でもたぶん大丈夫だ。
「ああッ、もっ、もういいっ、もうい……ッ、あぁッ!」
七尾は優しいから、絵日記と一緒に、ユキのことも丁寧に大切に、元に戻してくれるだろう。
日が昇りきった七尾の部屋で、窓の外から漏れてくる都会の朝の喧騒を聞きながら、ユキは正座させられていた。
「で? なんでこうなった」
靴下を履きながら、七尾は低く聞く。傍らには、これから行く予備校のテキストが積まれている。その隣には、ユキの専門学校用の鞄が用意されている。
「えっと、タケ……、な、七尾……起きないし? ヒマだから、直しとこっかなーって思ったら、なんか、なんでか、こんな感じに、なってて……」
二人の間には、テープで留められてはいるが、しわくちゃの絵日記が置かれている。波打ちすぎて文字が読めない。
「お前、手先だけは器用なんじゃないのか」
「そっ、そうなの! おれ普段型紙作ってるし、七尾よりは下手かもだけど大丈夫でしょって! ……や、これ大丈夫じゃない……よね……。ご、ごめん」
言いながら、どんどん険しくなる七尾の顔にユキは慄き、口を閉じた。七尾はしばらく黙ったあと、膝をつき人差し指でユキの胸を突いた。
「お前はもう二度とこれに触るな」
「で、でも元々これ、おれが描いたんだよ?」
「うるさい。いいか」
ぐっと七尾に肩を掴まれて、耳元で低く囁かれる。
「――次触ったら、お前が死ぬまでいかせ続けてやる」
さっきとは違う意味でユキは戦慄した。
一覧へ戻る
意外と濃いまつ毛に気付くと、朝から変な気分になってきて、ユキはいそいそと起き上がった。落ち着かない。初めて七尾の下宿先に泊まったからだろうか。そわそわしながらテープを手に取った。薄汚れた二枚の画用紙の端を合わせてみる。しかし、ふわぁとあくびが零れ、あっと思うとテープはよれてしまっていた。
「あーっ」
思わず声が出た。眉を下げ、いびつな角度で繋がった画用紙を掲げる。見慣れない窓の向こう、薄紫色の空に思い出を透かすと、甲高い二人の笑い声が聞こえた。
「下手くそ」
「わっ!」
日に焼けた腕で布団の中に引きずり込まれ、ぐっと抱き寄せられる。思い出はひらりと舞って、少し先の畳に落ちてしまう。
「お前はテープを切る係。貼るのはおれ。決めただろ」
「あ、そうだった、ごめん」
鼻先でユキを見つめる七尾の目は少し赤い。濃いまつ毛につい目がいくからか、色っぽく見える。昨日より、ドキドキする。
「……添い寝でよくそこまで、ニヤついて赤面できるな」
ユキは両手で頬を庇ったが、この距離では無意味だろう。七尾は抱き寄せたユキを見つめ、眠いのか顔をしかめる。そして赤い目を潤ませて、急に黙った。……なにか怒っているらしい。なんでだろう。
「……え? あれ? テープのこと? 違う? あっ、えーと、起こしちゃってごめん?」
「起こされてない」
「えっ。じゃあさっき起きてたの? おれまたバカなこと……」
「お前はなにもしてない」
「は? なにそれ」
きょとんとするユキに、七尾は、赤い目を見開いた。
「いいか。夕べいきなりお前はおれに会いに来た。ド平日の、日付変わって寝ようとしてた時にだ。明後日まで叔父さんたち旅行でいないにしても、学校あるからダメだってのに、一緒に寝るって散々駄々こねておれに抱きついて、そのまま本当に寝た。なにもしないでな。どうだ、少しはまだ覚えてるか」
「お、覚えてるよちゃんと。だから、今度は我慢するって謝ったじゃん、それに電車が」
「そうじゃない」
「えっ? あ。じゃあ、わかった! 一緒に寝てくれてありがとう!」
「違うバカ!」
ああもう、と七尾は頭を掻きむしり、黒髪がユキの顔に触れる。汗の匂いがさっきより甘い。それでなるほど、彼は興奮しているのかと気付いた。
「七、……んぅっ!」
深く口づけられ、再び抱き寄せられて、息が詰まるほど密着する。押し付けられた七尾のそこはすでに熱く猛り、ユキの出した答えを肯定していた。蕩けていく頭で、彼の身体がこんなにも反応している理由を思うと、熱い痺れがそこ一点に集中する。
「ぁ……ん……」
「クソバカ。一睡もできなかった」
かすれた声で七尾は言った。口づけを解かれたユキは、赤い目で寝返りを打ち、唸る彼を想像する。ちょっと可愛かった。
「そっ、それってさ……、おれとくっついて、ドキドキしてくれたってことだよね?」
「……その言い方はやめろ」
「でも、わっ!」
ばさりと布団を剥がされた。
七尾は見せつけるように、寝間着の上を脱ぐ。鍛え抜かれた身体が朝焼けに照らされて、ユキは溜息を零す。こんなにもしなやかな流線を、内から滲み出る力強さを、いつか自分の手で描くことが、形にすることができるのだろうか。
「なにぼさっとしてる。……脱げ」
低い声はまたかすれている。ユキは頷いて起き上がり、言われるがままワンピースになっている借り物のTシャツを脱ぐ。七尾が黙っているので、靴下も脱いでみるが、彼は口を閉じたままだ。
「え、まだ脱ぐの」
「お前はついに、自分で下着も脱げなくなったのか」
「そっ、そうじゃ、ないけど……」
七尾の裸は見惚れてしまってドキドキするが、男同士だし、自分のを見られるのはあまり気にならない。……ただ。
朝焼けが、布団に膝をつき向かい合う二人を照らす。熱い顔を隠すものはなにもない。子供のようなユキの手足も、――勃ち上がっているそこも、すべてが茜色の光の下に曝け出された。
「ずいぶん勃ってるな」
「あ、朝だからっ!」
子供の頃にはなかった「男」の部分を見られると、条件反射でいたたまれなくなってしまう。七尾はちゃんと、どんなユキでも好きだと言ってくれたのに。
「タ、タケちゃんだって、人のこと……、あ!」
七尾はユキの腕を掴んで引き、空いた手でいきなりそこを握る。かくんと腰を落とすと、そのまま組み敷かれた。
「待っ……!」
ひゅっと細い息が零れる。七尾は赤い目を細めてユキを見下ろし、口の端を上げる。
「もう待った」
低く短く言われてユキは悟った。……こうなった時の七尾はやばい。
「あっ、――あ! あっ、あっ、ああッ」
言葉はない。耳に差し込まれた舌と、ぬるつき始めたそこが、淫靡な音を立てユキの背をしならせる。
「はぁ、あぁ……」
仕留められた獲物のように首筋を噛まれ、息を詰まらせる。わずかな痛みと、滲んで広がる熱に震えながら、声にならない声を上げてユキは達した。
「……ぁ……ッ」
「……早いんだよ、だから」
七尾が顔を上げた。赤い目が、まだ足りないと言うように細まる。大人の七尾の顔だ。底の知れない淫らな予感に、ユキはぞくりとする。
「お前このまえ、何回いったっけか」
余韻にひくつくユキの身体をほぐすように仰向けにして、七尾は薄く笑う。
「試してみるか」
「……え……、な……に」
「大丈夫だ」
七尾の笑みは、すぐに見えなくなった。ユキが身体を反らし叫んだからだ。だって七尾が、さっき出したもので汚れたままの、まだ勃ったユキのそこを、舌で――……。
「だ……! いやっ、いやっ、ああ……っあっ!」
七尾に食べられていく。ぬるりとすべて呑み込まれて、ユキは首を振った。震える手で七尾の髪を引く。
「だ……めぇ……ッ! あッ、だ、おねが……ッ」
今すぐやめさせたいのに、一番気持ちいい先端を吸われ、そこに舌をねじ込まれると、頭が真っ白になってしまう。むしろ欲しがるように、自然と腰を突き出す自分に気付き、涙が零れた。
「やめ……、ひっ、やだ……、や、ひっ」
快感か羞恥か、それとも嫌悪か。ごちゃまぜの涙が頬を伝い、すぐそこまで迫った欲求に、ユキはしゃくりあげた。こうなったら止められないとわかっている。何度も何度も、七尾を思い浮かべて自分でした時に、嫌というほど思い知らされている。
「……で、……ちゃうぅ……ッ、……はっ……な……」
言葉を紡ぐ余裕もなく、ユキはただ泣いた。もうだめだ。最悪だ。大好きな七尾の口に汚いものを注ぎ込むのを想像して、びくびくと足を引き攣らせながら嗚咽を零した。
すると、ゆっくりと七尾の口が離れる。ユキがほっとするのも束の間、そこから顔を上げた彼は、とんでもないことを要求した。
「飲ませろ」
七尾の目は本気だ。意味がわからない。ユキは首を振り腰を引くが、身体ごと抱き上げられ、引き戻される。
「お、おねがい。ほ、ほかのことっ、なんでも、するから……」
「お前は何度か、ここでおれのを飲んだ」
「んん……っ」
ぬめった指で後孔をゆるゆるといじられ、びくんとそこが脈打つ。今ここで出せればと思うのに、根元をきゅっと握られてしまう。
「あッ、――ッ!」
「おれには、よこさない気か」
「な……っ、なんでっ、だって、きっ、汚いじゃんか!」
「汚くない」
「ひ……、う……んっ」
変わらない表情で短くそう言い、七尾はユキの根元を握ったまま、空いたほうの手を滑らせ、静かに指を埋めた。そして内側から絞り出すように、一気に追い立てる。
「なら一度でいい」
「あッ、ああぁッ」
「――ユキの、全部が欲しい」
薄い唇にそこを強く吸われ、ユキは叫んだ。根元を握られているから出せない。違う。出しちゃいけない。どうしたいのかわからない。
――七尾はユキのを飲むと、興奮するんだろうか。……ユキが七尾を全部呑み込む時、すごく幸せに思うのと同じように?
「ひぁ、――あッ、あぁ、ああぁ……っ」
思った瞬間、根元から七尾の手が離れ、ユキは射精した。
そこが脈打つのに合わせて、彼の喉が鳴る。なにもかも全部飲み込まれて、……混ざり合って、七尾の一部になってゆく。そう思うと、なぜか胸の奥が熱くなって、温かい涙が頬に一筋流れた。
「ユキ」
七尾は身体を起こして、気を使った声を出す。ユキの身体はまだ余韻でひくついていた。出してからずっと、胸にしみこんでくるこの気持ちの名前を知らない。だから七尾の首に縋りつく。宥めるように髪を撫でられた。
「もう大丈夫だ。もうしない」
「……や、おれも……、なんか、大丈夫……、かも……」
二人同時に顔を上げる。七尾はふっと眉を下げた。
「なんなんだバカ。だったらなんで嫌々言った」
ぎゅっと抱き寄せられて、その手がわずかに震えているのに気付き、息が詰まる。
「ご、ごめんっ、……はじめて、で……」
こんなに温かくて泣きそうな気持ちがあるなんて、知らなかった。
七尾はへの字の口をユキに押し付ける。反射的に口を開くユキの、好きなところを何度もなぞってくれる。そしてまた、ゆるゆるとユキの中心を握り始める。
「ん……。ねえ、おれ……は、もう、いいよ……、タケちゃんのほう……」
「お前さっき、なんでもするって言ったな」
「へ?」
「バカは本当、すぐ忘れるから困る」
低く七尾は笑って、ユキの耳を舐めながら囁いた。
「何回いけるか、試すって言っただろ」
返す言葉を見つける前に、全身を貪られて、吐息さえ唇で奪われて、蕩ける頭も身体もばらばらになってゆく。でもたぶん大丈夫だ。
「ああッ、もっ、もういいっ、もうい……ッ、あぁッ!」
七尾は優しいから、絵日記と一緒に、ユキのことも丁寧に大切に、元に戻してくれるだろう。
日が昇りきった七尾の部屋で、窓の外から漏れてくる都会の朝の喧騒を聞きながら、ユキは正座させられていた。
「で? なんでこうなった」
靴下を履きながら、七尾は低く聞く。傍らには、これから行く予備校のテキストが積まれている。その隣には、ユキの専門学校用の鞄が用意されている。
「えっと、タケ……、な、七尾……起きないし? ヒマだから、直しとこっかなーって思ったら、なんか、なんでか、こんな感じに、なってて……」
二人の間には、テープで留められてはいるが、しわくちゃの絵日記が置かれている。波打ちすぎて文字が読めない。
「お前、手先だけは器用なんじゃないのか」
「そっ、そうなの! おれ普段型紙作ってるし、七尾よりは下手かもだけど大丈夫でしょって! ……や、これ大丈夫じゃない……よね……。ご、ごめん」
言いながら、どんどん険しくなる七尾の顔にユキは慄き、口を閉じた。七尾はしばらく黙ったあと、膝をつき人差し指でユキの胸を突いた。
「お前はもう二度とこれに触るな」
「で、でも元々これ、おれが描いたんだよ?」
「うるさい。いいか」
ぐっと七尾に肩を掴まれて、耳元で低く囁かれる。
「――次触ったら、お前が死ぬまでいかせ続けてやる」
さっきとは違う意味でユキは戦慄した。