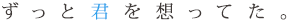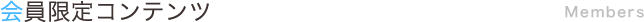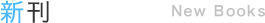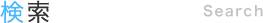祓い屋・木津恵信の荒ぶる性欲
――祓い屋・木津恵信の危うい恋人――
「八重山が手に負えないので助けてほしい」
警視庁総務部長の矢代から協力を要請されたのは事件解決から間もなくのことだった。
八重山は結界を施した特殊な独房に収容されていた。異例中の異例だそうだ。独房から出る際には拘束具を付けられ、厳重な警戒態勢の下で監視されていたが、供述を得ようと口枷を外した途端、取調べの担当者がペンで自らの目を突こうとしたらしい。止めに入った警官も次々と錯乱し収拾不能となり、やむなく中断したそうだ。
事件は厭魅係の担当ではなくなっていたが、このままでは埒が明かない、とのことで、取調べは僕の立ち合いのもと、厭魅係が行うことになった。
僕と盛田の姿を見て八重山は笑った。元気そうに見えるが、以前よりも白髪が目立ち、痩せたようだ。
「ようやく来はった。久しぶりやな。あれから一回も会いに来んで、この薄情もんが」
何を企んでいるのかと身構えたが、予想に反して八重山は僕に何も仕掛けてこなかった。
「ええと、まず、あの護符は一体あと何枚あるんだ?」
盛田が尋ねると八重山は意外にもあっさりと供述を始めた。
「覚えてへんよ。作れるだけ作ったし」
「八重山さん、頼むよ。そろそろ煙草が恋しいだろ? 覚えてる範囲でいい。教えてくれ」
ため息を吐きながら盛田が手を合わせると八重山は笑いながら答えた。
「はは、なんや、急に後輩ぶって可愛いなるやん。せやな、百万枚かそこらと違うか」
真面目に答える気はないらしい。盛田は諦めて別の質問を始めた。
「八重山さんが作ったあの護符だけどな。流通してた別のものを調べたら、全然効果がなかったらしいぜ。どういうことだ?」
八重山の背後に控えた一課の刑事が頷いた。
「そら、おかしいなあ。あんたら豚皮のパチモン掴まされたんとちゃうか。わざわざ言うてへんけど、チンピラどもがぎょうさん偽物作っとったで。本物なら効果は抜群や、お前らも知っとるやろ。嘘だと思うんなら、彼氏に聞いてみい」
八重山はおかしそうにのけ反って僕を見る。だが、目が合ったのは一瞬だった。故意に目を逸らしたようにも見えた。
八重山は何かを隠している?
しかし、この期に及んで一体何を隠すというのか。もはや失うものは何もないはずだ。
盛田は首を振った。
「いや違う。確かに偽物もあったが、俺らが調べたものは間違いなく人間の皮膚だった。それだけじゃねえ、皮の身元だ。男は山伏崩れ、女は若い頃に骨髄移植のドナーをやってる。徳は高いと言っていいだろ。夫婦で、どっちも高齢になってからの病死だ。葬儀屋が吐いたよ。葬儀の前にこっそりあんたに剥いだ皮を渡すように頼まれたってな」
盛田は八重山を覗き込んだ。
「条件はあの護符とほとんど同じなのに、効力がねえ理由はなんだ?」
盛田はテーブルに肘を突き、八重山ににじり寄った。
「術者自身が皮膚の持ち主に直接手を下すことが発動の条件だからなんじゃねえのか?」
八重山は父親と、路上生活者支援のボランティアをしていた女性の殺害および遺体損壊、死体遺棄の容疑をかけられている。捜査一課は大量の余罪があるとみているようだ。
だが、盛田の考えは違うらしい。祈るように八重山を見つめている。
「八重山さん、あんたもしかして、あの二人以外は誰も殺してないんじゃ……」
黙っている八重山のごま塩頭を眺めながら、僕は気が付いた。
ああ、あった。何もかも失った八重山が、たった一つ隠すもの。
「心……か」
「え?」
僕の呟きで盛田が振り返った。八重山は大きくため息を吐いて舌打ちした。
「木津先生、ほんま、あんた、ムカつくわ」
顔を上げた八重山は盛田を笑う。
「盛田、お前はおめでたいのか失礼なのかわからんのう。心配してくれはって。おおきに。殺されかけたの忘れたんか。しかもあの護符で何人死んだと思っとるん。でもなあ、僕はあの二人にだって直接手を下したりはしてへんで。他の奴らも少なくとも刑法で裁ける範囲では殺してへんよ。事後処理を手伝っただけや」
「じゃあ、なんでだ? あの護符は何が違うって言うん……だ……」
言いながら盛田も気が付いたようだ。はっとしたように口を噤んだ。
一瞬だけ八重山のやつれた顔が心細そうな少年のそれと重なって、すぐに元に戻る。
「なんでって、考えたらわかるやろ。盛田、これから厭魅係としてやってくなら、よう覚えとき。呪術で一番大事なんは感情やで」
古来より洋の東西を問わず、呪術の効力を高める最も効率的な方法は、愛する人の命を捧げることだ。大切な人を失った悲しみや罪悪感に勝る代償はない。八重山があの呪符を完成させられる死体は、この世には父親とその恋人の死体しかなかった。リスクを冒してまで護符を取り戻そうとしたのはそのせいもあるだろう。
非常に強力な呪符だとは思っていたが、あの呪符が要求する犠牲はそこまで大きなものだったのか。二人の人間の命でも足りず、術者の絶望まで必要だとは。
八重山は確かに父親を憎んでいた。だが、息子として愛してもいた。そうでなければ父親のために汚れ仕事などするものか。あの激しい憎悪は父親だけに向けたものではなかった。
「あのくそ親父、あの女と一緒にうどん食って笑っとったな。なんや、平気そうやないかって気い抜けて。こっちは必死こいて稼いできたのにあほらし。ほんで、何も持ってへんくせに二人して僕の心配しよる。金なんぞええから、一緒にうどん食え、言うんよ。なんやねん、ほんま、弱っちい貧乏人ども。片方シャブ中やし……くそ、何が悲しゅうてお前らにこんなこと言わなあかんねん」
惨めで間抜けな奴と思われるくらいやったら、極悪人でおった方がましやった、と八重山は顔を歪めて小さく零した。
「メロン買って帰ったら、畳の上で二人して死んどった。親父を殺った奴は知り合いや。皮肉なもんやで。僕っちゅう術者の後釜が現れて、親父は用済みになったんやと。あの女を庇うから面倒んなって、口封じも兼ねて殺したんやて。あいつ笑いよったわ」
――なんや、お前の親父だったんかい。ちょうどええわ。手伝い。死にたないやろ。
八重山は低く笑った。
「まあでも、翌年にはそいつも死んだ。あいつらあほやから、ちょっとええ思いさせたら、自分らは利用する側におるて、簡単に信じ込む」
そして、あの呪符により大勢のヤクザが死んだ。逆に言えば死んだのはヤクザだけだ。
八重山はまるで憎しみの全てをその小柄な身体の中に留めようとするかのごとく、背を丸めて俯く。八重山は乾いた声で言った。
「……ヤクザなんぞ、互いに殺し合って、全員おっ死ねばええ」
あの人皮の呪符は護符であると同時に、呪いそのものだった。
その後の取り調べはスムーズだった。八重山は憑き物が落ちたように、真面目に供述を始めた。おそらく元々そのつもりだったのだろう。僕らはまんまとおびき出されたのだ。
効力を発する人皮の呪符は、八重山が知る限り、この世に一枚しか存在しないそうで、僕はほっと胸を撫で下ろした。帰り際に八重山が言った。
「僕な、実はあんまり強くはないんよ」
あれだけのことをしておいて、何を言っているのか。呆気にとられる僕を八重山は笑った。
「ほんまやで。ここのぼんくらどもなんぞ屁でもないが、本物には敵わんわ。僕一人では大したことは何もできひん。怖いもんに力借りんとあかん。せやから盛田、お前にかけた呪いも、大したことない。元からあるもんを呼び起こしただけや。さっきも言うたやろ。呪いで一番大切なのは心やて」
八重山は意味ありげに盛田を見た。
「けどな、だからこそ、力の強さなんぞ関係なく、ごっつい効果出すことあんねん」
「一体何が言いたいんだ?」
盛田は怪訝な顔だ。
「はっ! 無自覚かいな。色惚け野郎が一丁前に刑事の面しおって、可愛いもんやな。ちょっとした仕返し、ちゅうか忠告みたいなもんや。木津先生、あんた苦労するで」
八重山は鼻で笑った。
「まあ、ええわ。一人でこっから逃げ出すんは無理そうやし、とりあえず仲良うしてや、お二人さん。刑事なんぞ、半分ヤクザみたいなもんやで。怖くてかなわんわ」
心底馬鹿にしたように、ひゃっひゃっひゃ、と笑う八重山に一課の刑事たちは色めき立つ。
「木津先生、あんたのことは嫌いやけど、あんたと盛田、それに矢代のおばちゃんなら他の奴よりはましや。なんかあったら僕に相談しい。ほな、またな」
僕と盛田を殺そうとしていたくせによく言えたものだ。あまりの図太さに呆れてしまう。
その後、矢代のもとへ挨拶に向かい、僕達は警視庁を後にした。
最寄り駅から自宅までの道を盛田と二人で並んで歩いた。盛田は半休を取ったそうで、このまま直帰していいと言われているらしい。
「八重山さんは一体何を……っ……考えてるんですかねっ……」
盛田さん! 若干裏返り気味の大声が閑静な住宅街に響き渡った。呪いによる発語を下手に我慢しようとしたせいか、余計に大きな声が出てしまう。慌てて口を押さえて辺りをきょろきょろと見回した。盛田のおかげで卑猥な言動はなくなったとはいえ、それでも近所迷惑には違いない。そんな僕を見て盛田は穏やかに笑う。
「そんなに気にしなくても平気だろ。まだ昼過ぎだし……なんとなくだけどよ、八重山さんが俺らに協力しようとしてるのは嘘じゃねえ気がするな。厭魅係に協力することで、取引狙ってんのかもしんねえぜ。俺にはよくわかんねえけど、八重山さんの呪術の知識はすげえんだろ?」
盛田はあっけらかんとしている。僕に対する八重山の激しい憎悪を思い出すと、とても信じられない。しかし確かに彼の裏社会の情報網や呪術の知識は今後捜査の役に立つだろう。
「それに、一課の奴らが悔しそうにしてたのは最高だったな」
盛田と僕が現れた途端、すらすらと供述を始めた八重山を見て、捜査一課の刑事たちは苦虫を噛みつぶしたような顔をしていた。思い出し笑いをしている盛田を見ていると、心配ばかりしているのも馬鹿らしい気がしてくる。
「報告を受けた矢代さんも、ちょっと嬉しそうでしたね」
「ははっ、そうだな」
「今回の事件を受けて……っ盛田さん……厭魅係の人員も増やしてもらえそうですよ。これから仕事も増えますね。僕も頑張らなきゃ」
矢代によると、二人の増員が予定されているそうだ。うち一人は盛田の後輩で、僕と盛田が出会うきっかけとなった痴漢事件の取り調べを担当した警官だという。
厭魅係に配属されるということは、そのうち僕とも関わることになるだろう。僕は彼女に失礼な発言をしてしまったので、心配していたが、矢代の話では彼女は僕と盛田と働けることを楽しみにしているそうだ。
盛田のおかげで僕は卑語を人前で口にすることはほとんどなくなった。「変な奴」には違いないだろうが、以前よりはだいぶましなはずだ。矢代も、これなら盛田以外の人間と働いても問題ないと請け合ってくれた。
だが、僕と盛田が恋人同士であることは、すぐに職場に知れ渡ってしまうだろう。僕はどう思われても構わないが、盛田の評判を落とすわけにはいかない。気を抜かないようにしなければ。
とはいえ、盛田に同僚ができるのは非常に喜ばしいことだ。盛田は仕事仲間を欲しがっていた。喜んでいるだろうと思って盛田を見上げたが、盛田は無言だ。
「盛田さん?」
上の空だ。去り際の八重山の言葉のせいだろうか。盛田は自分が呪いに操られて、八重山に護符を渡しそうになったことを気に病んでいた。八重山の言葉のせいで変に自分を責めていなければいいが。
「ん? ああ、そうだな。ようやく部下ができる。こき使ってやらねえと」
盛田は取り繕うように笑った。
「俺としては、もうしばらく二人きりの厭魅係も悪くねえと思ってたんだがな」
盛田は悪戯っぽく笑って流し目をくれた。思わず胸を押さえる。何度見ても心臓に悪い。
ああ、くそ、なんて可愛い顔なんだ。
このところずっとお預けを食らっていたこともあり、身体が熱くなってくる。
「そうそう、今回の件で若い刑事を中心に呪術の勉強したがる奴らが増えたらしいぜ。木津さんに呪術の講習会を頼みたいって矢代さんが言ってたぞ」
恋人の横顔に見惚れていると、とんでもない事を言われた。
そういった場は苦手だ。困惑気味の僕を見て盛田は楽しそうだ。
「俺は構わねえよ。思う存分、壇上で俺の名前を呼んでくれよ。なんなら『愛しの』って付けてくれてもいいぞ」
「え、いいんですか!? そうか……いいのか」
それはそれで悪くないかもしれない。盛田に近付く悪い虫を牽制できる。きっとこれから厭魅係の待遇がよくなるにつれて、盛田と関わる人間も増えるだろう。どう考えても盛田はモテる。きっと後輩の面倒もよく見るに違いない。盛田には言えないが、心配でたまらない。そんなことを考えているうちに家に着いた。
「木津さんちに帰るのは三週間ぶりか?」
「そうですね」
同居を決めてからすぐに防音工事や鍵の手配をし、先日ようやく工事が終わった。荷物をまとめるのを手伝うついでに、僕が盛田の家に行ったりはしていたのだが、お互いの仕事に邪魔されたこともあり、最近は二人でゆっくりする時間をなかなか取れないでいた。
しかし今日からはここで一緒に暮らせる。盛田が半休を取ったのは引っ越しのためだ。
「あらためて、これからよろしくな」
盛田は部屋のあちこちを見て回り嬉しそうにしている。荷物は午前中のうちに業者に運ばせてある。部屋の隅には盛田の荷物の段ボール箱が積まれている。
「壁が厚くなって多少狭くなるって聞いてたけど、元が広いから、ほとんどわかんねえな」
「お金出して下さって……盛田さんっ……ありがとうございます」
改装のための費用は盛田が持った。
「家賃の前払いみたいなもんだよ。これからご厄介になるからな」
「ばあちゃんと優ちゃんは、むしろありがたいって言ってましたよ。警察官が家にいるなんて安心だって」
「そういや、優希さん……は昼だから寝てるか。敦子さんは? 挨拶しねえと」
「ああ、買い物に行くってさっき連絡が」
会話が途切れた。どこかで犬が吠えている。表通りから車の音が微かに聞こえる。
「……あ、そ、そうだ。防音、確認します?」
鍵を付けたドアを閉め、ベッドにのぼり、換気のために開けていた小窓も閉めた。
「ほら、すごいんですよ。こうすると外の音が全然聞こえない」
「ほんとだな! これで、いつでもでけえ声上げてヤりたい放題ってわけか」
がはは、と盛田が笑う。僕も一緒に笑った。しかし、すぐに声が萎む。盛田は自分で言ったくせに、照れて真っ赤になっている。
思わず、ごくっと唾を飲んだ。
溜まりに溜まった性欲が喉元まで迫って苦しいくらいだった。
静かだ。まるで世界に僕と盛田の二人きりになってしまったかのように。
初秋の昼下がりの光の中で盛田が照れ臭そうに微笑んで僕を見つめていた。逞しい首の筋肉が光を弾いている。盛田が再び僕の部屋に来てくれた。ずっと待っていた。本当はもうどこへも行かせたくない。二度と危ない目に遭ってほしくない。
「……っ盛田さん……を、と、閉じ込めちゃおっかな……」
冗談にしては余りにも生々しい欲望に掠れた声が出て、自分自身に狼狽えた。
「ははっ、なんてね! 荷物開けないと。そうだ引っ越し祝いしましょう。今日はご馳走作りますよ……」
窓を開けようと、再びベッドの上で膝立ちになり手を伸ばした。するとベッドが大きく沈んで、僕の手の上に大きな手の平が重ねられた。盛田がベッドに乗り上げてきたのだ。背中に感じる体温に一気に心拍数が上がる。
「なんだよ……冗談なのか?」
振り返ると妖艶な笑みを浮かべた盛田の顔が間近にあった。吐息と共に低い声を耳に吹き込まれる。ただそれだけで、びくんと身体が反応した。
「あ……」
盛田の指がそっと僕の指をなぞった。盛田はそのまま僕の指を押して窓のロックを戻してしまう。官能的な仕草に思わず息が荒くなる。
「せっかく久しぶりに二人っきりなのによ。俺のこと閉じ込めてくれねえの?」
盛田が甘えるように、僕の首筋に頭を摺り寄せた。すっかり反応してテントを作っている僕の前をゆっくりと撫でる。
「はっ……あっ」
「なあ、行くなよ。引っ越し祝いは今度にしようぜ。なんで木津さんは、すぐどっか行こうとするんだよ」
拗ねたような子供じみた言い方だ。強烈な既視感がある。先程からあった違和感が、明確な形になった。
嘘だろ。今、盛田から呪いの気配はしないのに。
「部下ができるのは……そりゃ嬉しいけどよ」
だが、盛田の口調はまさに、呪われていた時のものだ。会話に矛盾点はないので、錯乱はしていないようだが、一体どういうことだろう。
「せっかくこれからは外でも木津さんと一緒にいられると思ったのに、もう二人きりじゃねえってことだろ……」
頬を染め少し口を尖らせながら、上目遣いでこちらに視線を寄越す。抱きしめる力が強くなる。
「だったらよ、家の中でくらい、二人っきりでいさせろよ……」
いつもの盛田ならこんなことは絶対に言わない、とは思った。だが、こんなの盛田じゃない、とは思わなかった。これは剥き出しの本心だ。そう思った瞬間に、呼吸を忘れるほど欲情した。
あの時は盛田を失うかもしれないという恐怖で、それどころではなかったが、僕はずっと、呪われて錯乱していた時の、あの無邪気で素直で明け透けで、それゆえ危ういほどに淫奔な気配を纏った盛田を、もう一度見てみたいと思っていたのだ。
「はは、そうこなくちゃな」
押し倒されながら満足げに微笑んだ盛田はいつもの盛田なのか、それともそうではないのか。僕にはわからなかった。
「あっ……あっ……あっ……こづさっ……はあ……んっ!」
盛田は僕の腰に筋肉でできた脚を絡めて腰を震わせた。
「くそ……っ、おっさんが……みっともねえ……よな……あっ」
僕に突き上げられ、盛田は悔しそうにのけ反った。
「少し前までは、ご無沙汰が……っく……当たり前……だったのによ……っ……っぁ」
軽く達したのか、こめかみをひくつかせながら盛田が言葉を切った。僕も思わず動きを止めた。盛田のそこは激しく収縮して僕を引き込む。危うく出してしまうところだった。
「今は、ちょっとお預け食らっただけで……こんなにガッついちまう……」
後ろで達した直後の緩んだ顔で盛田はふっと溜息を吐いた。今はいつもの抑制の効いた大人な盛田だ。憂いを帯びた顔に見惚れていると引き寄せられ唇を吸われた。
「ん……ふっ」
盛田の達したばかりの熱い奥を押しつぶすように、じりじりと腰を動かしながら、口付けに酔いしれた。互いの舌が触れ合うたびに、盛田のそこが戦慄く。
「く……っ」
それが辛かったのか、盛田は呻き声を上げて口を離した。うっすら目を開けると盛田は酩酊したように奇妙な美しい笑みを浮かべている。
「好きだぜ、なあ……どこも行くな。このままずっと二人でここにいよう、な?」
かと思えば、また淫靡な欲望を曝け出す盛田になった。さっきまでは、久しぶりの行為に年甲斐もなく昂ぶる己を自嘲していた。しかし今はまるで僕を篭絡しようとする妖しい生き物のようだ。
「俺さえいれば、それでいいだろ?」
太い腿が、筋肉で張った脛が僕の腰をぎゅっと締め付ける。
僕はそれでいいかもしれないが、彼には広い世界が似合う。だが、盛田はそんなことはすっかり忘れてしまったかのようだ。
「ん……っ、なあって」
甘えた声で盛田が返事を強請る。いつもは思慮深い盛田が。
「……っ」
ぎちっと音がしそうなほど、盛田の中で僕の陰茎が反り返った。
この駄々をこねる盛田の破壊力ときたら。今すぐ盛田の脚を思い切り開かせて手酷く犯してやりたい。だが、頭の冷静な部分は分析をやめない。
八重山が言っていたのはこういうことか。
元からあるものを呼び起こしただけ、だからこそ、根深く、強い影響を及ぼす。
おそらく恋人に強い執着心と独占欲を示す盛田は、彼の中に元々いたのだろう。それが呪いによって自覚され、明確な意志を持って表に出てきた。
どちらの盛田なのかわからなくなるのも無理はない。もとより境界線などない。どちらも盛田であって切り離すことはできないのだ。八重山の呪いは強いものではなく、呪い自体はすでに消えているが、盛田の精神に一生消えない痕跡を残した。
盛田のためを思うのなら、きっぱりと否定すべきなのかもしれない。だが僕は、そんな嘘は言いたくなかった。
「ええ……そうですね。あなたがいれば、それでいい」
正直に答えると盛田は子供のように顔中で笑った。
「へへっ……そうだろ、そうだろ……へへへ、俺も」
こんな関係は不健全だ、と言う人もいるだろうが、僕に不安はなかった。そもそも、心の隅々まで健全な人間など、はたしてこの世にいるだろうか。僕だって呪われている。そして僕の心も清廉潔白とは言えない。
僕も笑った。きっと盛田と同じ無邪気な笑みを顔に浮かべて。
「盛田さん……っ……好きです……っ僕の、盛田さん……っ……」
「俺だけ……見てろ……よ、誰にもやらねえ。んは、あ……あっ! ……んっんっんっ……ふ」
欲望のままに盛田を責め立てた。
真面目で寛大で、常に他人を思い遣る盛田が、唯一自分本位になるのが僕の前なのだとしたら、それは光栄で幸せなことだ。なんのことはない。盛田が前より少し素直になっただけのことだ。何も心配はいらない。
「ああっ!! ……っ!?」
しかし、盛田は奥を強く抉られ大声を上げた瞬間に、また冷静さを取り戻してしまった。
「すげえ、声……出た、わ、わりい……っんふっ……っ」
慌てたように口を押さえ、きつく目を瞑って強過ぎる快感に耐えようとしている。
この快楽に溺れながらも自制心を捨てきれない盛田も、それはそれで凄まじく僕を煽るが、もっと油断してくれていいのに。
「大丈夫ですよ……忘れちゃったんですか?」
にっこり笑って優しく盛田の手首を掴み、ゆっくりと彼の顔の横に縫い付ける。青い炎が漂う。あまりにもあっさりと押さえ込まれて、盛田は戸惑ったように目を瞬かせた。
「そのための防音工事です」
僕の前では何も隠さなくていい。
「いや、……え? ちょ……まっ……はあっ……く、あ、あ、あ……あっ! はあ……っ」
なす術もなく、喘ぎ声を垂れ流すしかなくなった盛田の目が、また欲望に霞んでいく。舌を出し、だらしなく乱れながら、うっとりと蠱惑的な笑みを浮かべ始める。
盛田の言う通りだ。せめてこの家の中でくらいは、僕も盛田も欲望に素直になってもいい。
仄暗い情念だって、人と違う部分だって、今は無理に抑え込まなくていい。消さなくていい。捨てなくていい。僕にかけられた呪いごと、盛田が僕を愛してくれたように。
ふと、部屋の隅に積まれた段ボール箱が目に入った。
「こら……よそ見……んっ……すんなって」
だが、見なかったことにした。
しばらく引っ越し作業は進みそうにない。
一覧へ戻る
「八重山が手に負えないので助けてほしい」
警視庁総務部長の矢代から協力を要請されたのは事件解決から間もなくのことだった。
八重山は結界を施した特殊な独房に収容されていた。異例中の異例だそうだ。独房から出る際には拘束具を付けられ、厳重な警戒態勢の下で監視されていたが、供述を得ようと口枷を外した途端、取調べの担当者がペンで自らの目を突こうとしたらしい。止めに入った警官も次々と錯乱し収拾不能となり、やむなく中断したそうだ。
事件は厭魅係の担当ではなくなっていたが、このままでは埒が明かない、とのことで、取調べは僕の立ち合いのもと、厭魅係が行うことになった。
僕と盛田の姿を見て八重山は笑った。元気そうに見えるが、以前よりも白髪が目立ち、痩せたようだ。
「ようやく来はった。久しぶりやな。あれから一回も会いに来んで、この薄情もんが」
何を企んでいるのかと身構えたが、予想に反して八重山は僕に何も仕掛けてこなかった。
「ええと、まず、あの護符は一体あと何枚あるんだ?」
盛田が尋ねると八重山は意外にもあっさりと供述を始めた。
「覚えてへんよ。作れるだけ作ったし」
「八重山さん、頼むよ。そろそろ煙草が恋しいだろ? 覚えてる範囲でいい。教えてくれ」
ため息を吐きながら盛田が手を合わせると八重山は笑いながら答えた。
「はは、なんや、急に後輩ぶって可愛いなるやん。せやな、百万枚かそこらと違うか」
真面目に答える気はないらしい。盛田は諦めて別の質問を始めた。
「八重山さんが作ったあの護符だけどな。流通してた別のものを調べたら、全然効果がなかったらしいぜ。どういうことだ?」
八重山の背後に控えた一課の刑事が頷いた。
「そら、おかしいなあ。あんたら豚皮のパチモン掴まされたんとちゃうか。わざわざ言うてへんけど、チンピラどもがぎょうさん偽物作っとったで。本物なら効果は抜群や、お前らも知っとるやろ。嘘だと思うんなら、彼氏に聞いてみい」
八重山はおかしそうにのけ反って僕を見る。だが、目が合ったのは一瞬だった。故意に目を逸らしたようにも見えた。
八重山は何かを隠している?
しかし、この期に及んで一体何を隠すというのか。もはや失うものは何もないはずだ。
盛田は首を振った。
「いや違う。確かに偽物もあったが、俺らが調べたものは間違いなく人間の皮膚だった。それだけじゃねえ、皮の身元だ。男は山伏崩れ、女は若い頃に骨髄移植のドナーをやってる。徳は高いと言っていいだろ。夫婦で、どっちも高齢になってからの病死だ。葬儀屋が吐いたよ。葬儀の前にこっそりあんたに剥いだ皮を渡すように頼まれたってな」
盛田は八重山を覗き込んだ。
「条件はあの護符とほとんど同じなのに、効力がねえ理由はなんだ?」
盛田はテーブルに肘を突き、八重山ににじり寄った。
「術者自身が皮膚の持ち主に直接手を下すことが発動の条件だからなんじゃねえのか?」
八重山は父親と、路上生活者支援のボランティアをしていた女性の殺害および遺体損壊、死体遺棄の容疑をかけられている。捜査一課は大量の余罪があるとみているようだ。
だが、盛田の考えは違うらしい。祈るように八重山を見つめている。
「八重山さん、あんたもしかして、あの二人以外は誰も殺してないんじゃ……」
黙っている八重山のごま塩頭を眺めながら、僕は気が付いた。
ああ、あった。何もかも失った八重山が、たった一つ隠すもの。
「心……か」
「え?」
僕の呟きで盛田が振り返った。八重山は大きくため息を吐いて舌打ちした。
「木津先生、ほんま、あんた、ムカつくわ」
顔を上げた八重山は盛田を笑う。
「盛田、お前はおめでたいのか失礼なのかわからんのう。心配してくれはって。おおきに。殺されかけたの忘れたんか。しかもあの護符で何人死んだと思っとるん。でもなあ、僕はあの二人にだって直接手を下したりはしてへんで。他の奴らも少なくとも刑法で裁ける範囲では殺してへんよ。事後処理を手伝っただけや」
「じゃあ、なんでだ? あの護符は何が違うって言うん……だ……」
言いながら盛田も気が付いたようだ。はっとしたように口を噤んだ。
一瞬だけ八重山のやつれた顔が心細そうな少年のそれと重なって、すぐに元に戻る。
「なんでって、考えたらわかるやろ。盛田、これから厭魅係としてやってくなら、よう覚えとき。呪術で一番大事なんは感情やで」
古来より洋の東西を問わず、呪術の効力を高める最も効率的な方法は、愛する人の命を捧げることだ。大切な人を失った悲しみや罪悪感に勝る代償はない。八重山があの呪符を完成させられる死体は、この世には父親とその恋人の死体しかなかった。リスクを冒してまで護符を取り戻そうとしたのはそのせいもあるだろう。
非常に強力な呪符だとは思っていたが、あの呪符が要求する犠牲はそこまで大きなものだったのか。二人の人間の命でも足りず、術者の絶望まで必要だとは。
八重山は確かに父親を憎んでいた。だが、息子として愛してもいた。そうでなければ父親のために汚れ仕事などするものか。あの激しい憎悪は父親だけに向けたものではなかった。
「あのくそ親父、あの女と一緒にうどん食って笑っとったな。なんや、平気そうやないかって気い抜けて。こっちは必死こいて稼いできたのにあほらし。ほんで、何も持ってへんくせに二人して僕の心配しよる。金なんぞええから、一緒にうどん食え、言うんよ。なんやねん、ほんま、弱っちい貧乏人ども。片方シャブ中やし……くそ、何が悲しゅうてお前らにこんなこと言わなあかんねん」
惨めで間抜けな奴と思われるくらいやったら、極悪人でおった方がましやった、と八重山は顔を歪めて小さく零した。
「メロン買って帰ったら、畳の上で二人して死んどった。親父を殺った奴は知り合いや。皮肉なもんやで。僕っちゅう術者の後釜が現れて、親父は用済みになったんやと。あの女を庇うから面倒んなって、口封じも兼ねて殺したんやて。あいつ笑いよったわ」
――なんや、お前の親父だったんかい。ちょうどええわ。手伝い。死にたないやろ。
八重山は低く笑った。
「まあでも、翌年にはそいつも死んだ。あいつらあほやから、ちょっとええ思いさせたら、自分らは利用する側におるて、簡単に信じ込む」
そして、あの呪符により大勢のヤクザが死んだ。逆に言えば死んだのはヤクザだけだ。
八重山はまるで憎しみの全てをその小柄な身体の中に留めようとするかのごとく、背を丸めて俯く。八重山は乾いた声で言った。
「……ヤクザなんぞ、互いに殺し合って、全員おっ死ねばええ」
あの人皮の呪符は護符であると同時に、呪いそのものだった。
その後の取り調べはスムーズだった。八重山は憑き物が落ちたように、真面目に供述を始めた。おそらく元々そのつもりだったのだろう。僕らはまんまとおびき出されたのだ。
効力を発する人皮の呪符は、八重山が知る限り、この世に一枚しか存在しないそうで、僕はほっと胸を撫で下ろした。帰り際に八重山が言った。
「僕な、実はあんまり強くはないんよ」
あれだけのことをしておいて、何を言っているのか。呆気にとられる僕を八重山は笑った。
「ほんまやで。ここのぼんくらどもなんぞ屁でもないが、本物には敵わんわ。僕一人では大したことは何もできひん。怖いもんに力借りんとあかん。せやから盛田、お前にかけた呪いも、大したことない。元からあるもんを呼び起こしただけや。さっきも言うたやろ。呪いで一番大切なのは心やて」
八重山は意味ありげに盛田を見た。
「けどな、だからこそ、力の強さなんぞ関係なく、ごっつい効果出すことあんねん」
「一体何が言いたいんだ?」
盛田は怪訝な顔だ。
「はっ! 無自覚かいな。色惚け野郎が一丁前に刑事の面しおって、可愛いもんやな。ちょっとした仕返し、ちゅうか忠告みたいなもんや。木津先生、あんた苦労するで」
八重山は鼻で笑った。
「まあ、ええわ。一人でこっから逃げ出すんは無理そうやし、とりあえず仲良うしてや、お二人さん。刑事なんぞ、半分ヤクザみたいなもんやで。怖くてかなわんわ」
心底馬鹿にしたように、ひゃっひゃっひゃ、と笑う八重山に一課の刑事たちは色めき立つ。
「木津先生、あんたのことは嫌いやけど、あんたと盛田、それに矢代のおばちゃんなら他の奴よりはましや。なんかあったら僕に相談しい。ほな、またな」
僕と盛田を殺そうとしていたくせによく言えたものだ。あまりの図太さに呆れてしまう。
その後、矢代のもとへ挨拶に向かい、僕達は警視庁を後にした。
最寄り駅から自宅までの道を盛田と二人で並んで歩いた。盛田は半休を取ったそうで、このまま直帰していいと言われているらしい。
「八重山さんは一体何を……っ……考えてるんですかねっ……」
盛田さん! 若干裏返り気味の大声が閑静な住宅街に響き渡った。呪いによる発語を下手に我慢しようとしたせいか、余計に大きな声が出てしまう。慌てて口を押さえて辺りをきょろきょろと見回した。盛田のおかげで卑猥な言動はなくなったとはいえ、それでも近所迷惑には違いない。そんな僕を見て盛田は穏やかに笑う。
「そんなに気にしなくても平気だろ。まだ昼過ぎだし……なんとなくだけどよ、八重山さんが俺らに協力しようとしてるのは嘘じゃねえ気がするな。厭魅係に協力することで、取引狙ってんのかもしんねえぜ。俺にはよくわかんねえけど、八重山さんの呪術の知識はすげえんだろ?」
盛田はあっけらかんとしている。僕に対する八重山の激しい憎悪を思い出すと、とても信じられない。しかし確かに彼の裏社会の情報網や呪術の知識は今後捜査の役に立つだろう。
「それに、一課の奴らが悔しそうにしてたのは最高だったな」
盛田と僕が現れた途端、すらすらと供述を始めた八重山を見て、捜査一課の刑事たちは苦虫を噛みつぶしたような顔をしていた。思い出し笑いをしている盛田を見ていると、心配ばかりしているのも馬鹿らしい気がしてくる。
「報告を受けた矢代さんも、ちょっと嬉しそうでしたね」
「ははっ、そうだな」
「今回の事件を受けて……っ盛田さん……厭魅係の人員も増やしてもらえそうですよ。これから仕事も増えますね。僕も頑張らなきゃ」
矢代によると、二人の増員が予定されているそうだ。うち一人は盛田の後輩で、僕と盛田が出会うきっかけとなった痴漢事件の取り調べを担当した警官だという。
厭魅係に配属されるということは、そのうち僕とも関わることになるだろう。僕は彼女に失礼な発言をしてしまったので、心配していたが、矢代の話では彼女は僕と盛田と働けることを楽しみにしているそうだ。
盛田のおかげで僕は卑語を人前で口にすることはほとんどなくなった。「変な奴」には違いないだろうが、以前よりはだいぶましなはずだ。矢代も、これなら盛田以外の人間と働いても問題ないと請け合ってくれた。
だが、僕と盛田が恋人同士であることは、すぐに職場に知れ渡ってしまうだろう。僕はどう思われても構わないが、盛田の評判を落とすわけにはいかない。気を抜かないようにしなければ。
とはいえ、盛田に同僚ができるのは非常に喜ばしいことだ。盛田は仕事仲間を欲しがっていた。喜んでいるだろうと思って盛田を見上げたが、盛田は無言だ。
「盛田さん?」
上の空だ。去り際の八重山の言葉のせいだろうか。盛田は自分が呪いに操られて、八重山に護符を渡しそうになったことを気に病んでいた。八重山の言葉のせいで変に自分を責めていなければいいが。
「ん? ああ、そうだな。ようやく部下ができる。こき使ってやらねえと」
盛田は取り繕うように笑った。
「俺としては、もうしばらく二人きりの厭魅係も悪くねえと思ってたんだがな」
盛田は悪戯っぽく笑って流し目をくれた。思わず胸を押さえる。何度見ても心臓に悪い。
ああ、くそ、なんて可愛い顔なんだ。
このところずっとお預けを食らっていたこともあり、身体が熱くなってくる。
「そうそう、今回の件で若い刑事を中心に呪術の勉強したがる奴らが増えたらしいぜ。木津さんに呪術の講習会を頼みたいって矢代さんが言ってたぞ」
恋人の横顔に見惚れていると、とんでもない事を言われた。
そういった場は苦手だ。困惑気味の僕を見て盛田は楽しそうだ。
「俺は構わねえよ。思う存分、壇上で俺の名前を呼んでくれよ。なんなら『愛しの』って付けてくれてもいいぞ」
「え、いいんですか!? そうか……いいのか」
それはそれで悪くないかもしれない。盛田に近付く悪い虫を牽制できる。きっとこれから厭魅係の待遇がよくなるにつれて、盛田と関わる人間も増えるだろう。どう考えても盛田はモテる。きっと後輩の面倒もよく見るに違いない。盛田には言えないが、心配でたまらない。そんなことを考えているうちに家に着いた。
「木津さんちに帰るのは三週間ぶりか?」
「そうですね」
同居を決めてからすぐに防音工事や鍵の手配をし、先日ようやく工事が終わった。荷物をまとめるのを手伝うついでに、僕が盛田の家に行ったりはしていたのだが、お互いの仕事に邪魔されたこともあり、最近は二人でゆっくりする時間をなかなか取れないでいた。
しかし今日からはここで一緒に暮らせる。盛田が半休を取ったのは引っ越しのためだ。
「あらためて、これからよろしくな」
盛田は部屋のあちこちを見て回り嬉しそうにしている。荷物は午前中のうちに業者に運ばせてある。部屋の隅には盛田の荷物の段ボール箱が積まれている。
「壁が厚くなって多少狭くなるって聞いてたけど、元が広いから、ほとんどわかんねえな」
「お金出して下さって……盛田さんっ……ありがとうございます」
改装のための費用は盛田が持った。
「家賃の前払いみたいなもんだよ。これからご厄介になるからな」
「ばあちゃんと優ちゃんは、むしろありがたいって言ってましたよ。警察官が家にいるなんて安心だって」
「そういや、優希さん……は昼だから寝てるか。敦子さんは? 挨拶しねえと」
「ああ、買い物に行くってさっき連絡が」
会話が途切れた。どこかで犬が吠えている。表通りから車の音が微かに聞こえる。
「……あ、そ、そうだ。防音、確認します?」
鍵を付けたドアを閉め、ベッドにのぼり、換気のために開けていた小窓も閉めた。
「ほら、すごいんですよ。こうすると外の音が全然聞こえない」
「ほんとだな! これで、いつでもでけえ声上げてヤりたい放題ってわけか」
がはは、と盛田が笑う。僕も一緒に笑った。しかし、すぐに声が萎む。盛田は自分で言ったくせに、照れて真っ赤になっている。
思わず、ごくっと唾を飲んだ。
溜まりに溜まった性欲が喉元まで迫って苦しいくらいだった。
静かだ。まるで世界に僕と盛田の二人きりになってしまったかのように。
初秋の昼下がりの光の中で盛田が照れ臭そうに微笑んで僕を見つめていた。逞しい首の筋肉が光を弾いている。盛田が再び僕の部屋に来てくれた。ずっと待っていた。本当はもうどこへも行かせたくない。二度と危ない目に遭ってほしくない。
「……っ盛田さん……を、と、閉じ込めちゃおっかな……」
冗談にしては余りにも生々しい欲望に掠れた声が出て、自分自身に狼狽えた。
「ははっ、なんてね! 荷物開けないと。そうだ引っ越し祝いしましょう。今日はご馳走作りますよ……」
窓を開けようと、再びベッドの上で膝立ちになり手を伸ばした。するとベッドが大きく沈んで、僕の手の上に大きな手の平が重ねられた。盛田がベッドに乗り上げてきたのだ。背中に感じる体温に一気に心拍数が上がる。
「なんだよ……冗談なのか?」
振り返ると妖艶な笑みを浮かべた盛田の顔が間近にあった。吐息と共に低い声を耳に吹き込まれる。ただそれだけで、びくんと身体が反応した。
「あ……」
盛田の指がそっと僕の指をなぞった。盛田はそのまま僕の指を押して窓のロックを戻してしまう。官能的な仕草に思わず息が荒くなる。
「せっかく久しぶりに二人っきりなのによ。俺のこと閉じ込めてくれねえの?」
盛田が甘えるように、僕の首筋に頭を摺り寄せた。すっかり反応してテントを作っている僕の前をゆっくりと撫でる。
「はっ……あっ」
「なあ、行くなよ。引っ越し祝いは今度にしようぜ。なんで木津さんは、すぐどっか行こうとするんだよ」
拗ねたような子供じみた言い方だ。強烈な既視感がある。先程からあった違和感が、明確な形になった。
嘘だろ。今、盛田から呪いの気配はしないのに。
「部下ができるのは……そりゃ嬉しいけどよ」
だが、盛田の口調はまさに、呪われていた時のものだ。会話に矛盾点はないので、錯乱はしていないようだが、一体どういうことだろう。
「せっかくこれからは外でも木津さんと一緒にいられると思ったのに、もう二人きりじゃねえってことだろ……」
頬を染め少し口を尖らせながら、上目遣いでこちらに視線を寄越す。抱きしめる力が強くなる。
「だったらよ、家の中でくらい、二人っきりでいさせろよ……」
いつもの盛田ならこんなことは絶対に言わない、とは思った。だが、こんなの盛田じゃない、とは思わなかった。これは剥き出しの本心だ。そう思った瞬間に、呼吸を忘れるほど欲情した。
あの時は盛田を失うかもしれないという恐怖で、それどころではなかったが、僕はずっと、呪われて錯乱していた時の、あの無邪気で素直で明け透けで、それゆえ危ういほどに淫奔な気配を纏った盛田を、もう一度見てみたいと思っていたのだ。
「はは、そうこなくちゃな」
押し倒されながら満足げに微笑んだ盛田はいつもの盛田なのか、それともそうではないのか。僕にはわからなかった。
「あっ……あっ……あっ……こづさっ……はあ……んっ!」
盛田は僕の腰に筋肉でできた脚を絡めて腰を震わせた。
「くそ……っ、おっさんが……みっともねえ……よな……あっ」
僕に突き上げられ、盛田は悔しそうにのけ反った。
「少し前までは、ご無沙汰が……っく……当たり前……だったのによ……っ……っぁ」
軽く達したのか、こめかみをひくつかせながら盛田が言葉を切った。僕も思わず動きを止めた。盛田のそこは激しく収縮して僕を引き込む。危うく出してしまうところだった。
「今は、ちょっとお預け食らっただけで……こんなにガッついちまう……」
後ろで達した直後の緩んだ顔で盛田はふっと溜息を吐いた。今はいつもの抑制の効いた大人な盛田だ。憂いを帯びた顔に見惚れていると引き寄せられ唇を吸われた。
「ん……ふっ」
盛田の達したばかりの熱い奥を押しつぶすように、じりじりと腰を動かしながら、口付けに酔いしれた。互いの舌が触れ合うたびに、盛田のそこが戦慄く。
「く……っ」
それが辛かったのか、盛田は呻き声を上げて口を離した。うっすら目を開けると盛田は酩酊したように奇妙な美しい笑みを浮かべている。
「好きだぜ、なあ……どこも行くな。このままずっと二人でここにいよう、な?」
かと思えば、また淫靡な欲望を曝け出す盛田になった。さっきまでは、久しぶりの行為に年甲斐もなく昂ぶる己を自嘲していた。しかし今はまるで僕を篭絡しようとする妖しい生き物のようだ。
「俺さえいれば、それでいいだろ?」
太い腿が、筋肉で張った脛が僕の腰をぎゅっと締め付ける。
僕はそれでいいかもしれないが、彼には広い世界が似合う。だが、盛田はそんなことはすっかり忘れてしまったかのようだ。
「ん……っ、なあって」
甘えた声で盛田が返事を強請る。いつもは思慮深い盛田が。
「……っ」
ぎちっと音がしそうなほど、盛田の中で僕の陰茎が反り返った。
この駄々をこねる盛田の破壊力ときたら。今すぐ盛田の脚を思い切り開かせて手酷く犯してやりたい。だが、頭の冷静な部分は分析をやめない。
八重山が言っていたのはこういうことか。
元からあるものを呼び起こしただけ、だからこそ、根深く、強い影響を及ぼす。
おそらく恋人に強い執着心と独占欲を示す盛田は、彼の中に元々いたのだろう。それが呪いによって自覚され、明確な意志を持って表に出てきた。
どちらの盛田なのかわからなくなるのも無理はない。もとより境界線などない。どちらも盛田であって切り離すことはできないのだ。八重山の呪いは強いものではなく、呪い自体はすでに消えているが、盛田の精神に一生消えない痕跡を残した。
盛田のためを思うのなら、きっぱりと否定すべきなのかもしれない。だが僕は、そんな嘘は言いたくなかった。
「ええ……そうですね。あなたがいれば、それでいい」
正直に答えると盛田は子供のように顔中で笑った。
「へへっ……そうだろ、そうだろ……へへへ、俺も」
こんな関係は不健全だ、と言う人もいるだろうが、僕に不安はなかった。そもそも、心の隅々まで健全な人間など、はたしてこの世にいるだろうか。僕だって呪われている。そして僕の心も清廉潔白とは言えない。
僕も笑った。きっと盛田と同じ無邪気な笑みを顔に浮かべて。
「盛田さん……っ……好きです……っ僕の、盛田さん……っ……」
「俺だけ……見てろ……よ、誰にもやらねえ。んは、あ……あっ! ……んっんっんっ……ふ」
欲望のままに盛田を責め立てた。
真面目で寛大で、常に他人を思い遣る盛田が、唯一自分本位になるのが僕の前なのだとしたら、それは光栄で幸せなことだ。なんのことはない。盛田が前より少し素直になっただけのことだ。何も心配はいらない。
「ああっ!! ……っ!?」
しかし、盛田は奥を強く抉られ大声を上げた瞬間に、また冷静さを取り戻してしまった。
「すげえ、声……出た、わ、わりい……っんふっ……っ」
慌てたように口を押さえ、きつく目を瞑って強過ぎる快感に耐えようとしている。
この快楽に溺れながらも自制心を捨てきれない盛田も、それはそれで凄まじく僕を煽るが、もっと油断してくれていいのに。
「大丈夫ですよ……忘れちゃったんですか?」
にっこり笑って優しく盛田の手首を掴み、ゆっくりと彼の顔の横に縫い付ける。青い炎が漂う。あまりにもあっさりと押さえ込まれて、盛田は戸惑ったように目を瞬かせた。
「そのための防音工事です」
僕の前では何も隠さなくていい。
「いや、……え? ちょ……まっ……はあっ……く、あ、あ、あ……あっ! はあ……っ」
なす術もなく、喘ぎ声を垂れ流すしかなくなった盛田の目が、また欲望に霞んでいく。舌を出し、だらしなく乱れながら、うっとりと蠱惑的な笑みを浮かべ始める。
盛田の言う通りだ。せめてこの家の中でくらいは、僕も盛田も欲望に素直になってもいい。
仄暗い情念だって、人と違う部分だって、今は無理に抑え込まなくていい。消さなくていい。捨てなくていい。僕にかけられた呪いごと、盛田が僕を愛してくれたように。
ふと、部屋の隅に積まれた段ボール箱が目に入った。
「こら……よそ見……んっ……すんなって」
だが、見なかったことにした。
しばらく引っ越し作業は進みそうにない。