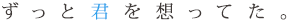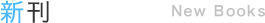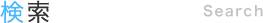「俺はこの日を待ち望んでいた!」
不慮の事故で『血を糧とする鬼』として目覚めてしまった海里の前に現れた吸血鬼のルカ。
ルカは自らを海里の守護者(ルビ:ガーディアン)と言いほぼ毎日海里につきまとい、
事あるごとに「海里は可愛い」と豪語してくる。
夜にはルカに血を吸われ、絶え間ない快感に翻弄されながらも、
海里はその感触になぜか安心感を覚えていく。
人でなくなった自分を理解し傍にいてくれるルカとずっと一緒にいたいと願うけれど、
吸血鬼同士の食糧問題が発生して……!?
オンライン書店
電子書店
登場人物紹介
-

- 花峰海里(はなみねかいり)
母を幼いころに事故で亡くしてから、父とのふたり暮らし。
-

- ルカ
試し読み
「嫌だってば! 放してって言ってるでしょ!」
「なんだと、生意気な口ききやがって! 減るもんじゃねえだろ、けちけちすんな!」
──どう見ても、カップルじゃないよな。
夜間のアルバイトを終え、繁華街の大通りから一本裏に入った道を歩いていた海里 は、揉めている男女の会話を耳にしてそう判断する。
見た目にしても男性の髪には白いものが交じっているし、女性は髪を金色に染めてはいるものの、顔立ちはもしかしたら未成年ではないかと思うくらいに、幼く見えた。
海里は暴力が嫌いだし、他人の揉め事に首を突っ込む趣味もない。けれどこの現場を黙って見過ごせるほど、冷たい性格というわけでもなかった。思わず男の背後に近寄ると、その肩に手をかける。
「嫌がってるじゃないですか。やめましょうよ」
海里の声に、男は酒臭い息をまき散らしながらこちらを振り向く。
「ああ? 誰だ、てめえは。文句あんのか」
「ただの通りすがりです。文句っていうか、これを見過ごすと人としてどうなのって、自分を嫌いになっちゃいそうなんで」
なにい? と男は酔った赤い目で、こちらを睨みつけてきた。同時に女性から手を放したので、海里は早く逃げろと目で合図をする。女性はペコッと頭を下げると、一目散に駆け出した。
「あっ、畜生、逃げちまったじゃねえか」
後を追おうとする男の腕を、そうはさせまいと海里がつかむ。
「もう行っちゃいました。あきらめましょうよ、みっともない」
「この野郎、人を馬鹿にしてるのか」
力任せに海里の腕を振りほどくと、男は懐に手を入れる。
「もうちょっとだったのに、邪魔しやがって!」
その手を見て、海里は息を呑んだ。折り畳み式のナイフが握られていたからだ。
わっ、と斬りかかってきた腕をはらいのけると、痛え! と男が悲鳴を上げる。はずみで自分の、反対側の手の甲を切ったらしい。
「痛えじゃねえか、てめえ! ぶっ殺してやる!」
──ああ、失敗した。まさかここまで危ない人だったとは思わなかった。でも逆に、俺が放っておいたらさっきの子、とんでもないことになってたかもしれない。勇気を出して、止めてよかった。
勝手に暴れて、勝手に自分で自分の手を切ったくせに、殺してやると凄むとは、八つ当たりもいいところだ。
それでも恐怖をあまり感じないのは、泥酔しているらしい男の手に大して力が入っておらず、足元もおぼつかない状態だからだろう。
ドン、とブロック塀に押し付けられた海里は、懸命にナイフを押し付けてくる男の手を押しとどめる。
「わかりました、俺が悪かったですから、こんなもの仕舞ってください! 危ないじゃないですか!」
「うるせえ、悪いと思ってるなら、おとなしく殺されろ!」
無茶苦茶なことを言いながら、男は執拗に海里に襲い掛かって来る。海里がナイフを持った腕を両手で押さえていると、男は血を流しているもう片方の手で、こちらの顔を壁にぐいぐいと押し付けてきた。
あまり力が入っていないので大して痛くはないのだが、頬に触れている男の手は血でぬるぬるとしている。その手はずるり、ずるりと下方に滑り、海里は顔をしかめた。
──わっ、気持ち悪い。手が口の近くに……!
顔を背けようとしたが、間に合わなかった。男の手の端が海里の唇に触れ、内側にまで血が付着する。鉄の味が口の中に広がった、刹那 。
ドクン、と全身が心臓になったかのように、大きく跳ねたのを海里は感じた。
──えっ。……なんだ、これ。
一瞬、目の前が赤く染まり、男も路地裏も、目に映るなにもかもが銀色に発光して見える。
「×××……! ××××!」
男がまたなにか叫んでいるが、なにを言っているのかわからない。
──なんだろう。目が、よく見えない。身体が、おかしい。
焦る海里は、男の背後に、誰かもうひとり別のシルエットを確認した。その途端、酔っ払いの男はくたくたとくずおれ、海里は誰かの腕に抱きとめられるのを感じる。
──駄目だ、もう……立っていられない。
海里は身体から力が抜けていくのを、自分ではどうすることもできず、とてつもない不安を感じながら、意識を失ってしまったのだった。
ふ、と目が覚めたのは、見慣れた家の前だった。
なぜか玄関横の塀を背に、海里は座った状態になっている。
「なんで俺、ここにいるんだ?」
つぶやくとなんだかくらくらして、海里は額を押さえた。
──確か、酔っ払いと揉み合いになったんだよな。それは覚えてる。……そうだ、それで……誰かが助けてくれた、ような。まさかその人が、ここまで連れてきてくれたのか? でも住所なんてわかるわけ……あ、財布の中の保険証を見たとか?
不思議に思いながらも海里は立ち上がり、腰や足の汚れを払って、ふらつきつつインターホンを押した。すぐに鍵を開ける音がして、内側からドアが開く。
「遅かったな、海里。心配するじゃないか」
顔を出したのは、海里の唯一の家族である父親の里史だった。
Tシャツとトランクスから痩せた手足がひょろりと覗き、なにも考えていなくともどこか悲しげな作りのその顔には、心配そうな表情が浮かんでいる。
「ごめん。なんか、酔っ払いに絡まれちゃって」
「大丈夫だったのか? まあいい、ともかく早く風呂に入って……」
言いながら里史は、玄関で靴を脱ぐ海里の顔にふと目を留め、次いで凝視した。
「おっ、おい、海里! 顔に血がついてるじゃないか!」
「血? ああ……あのときかな。その酔っ払い、どうしようもないやつでさ。ナイフ出してきたんだけど、自分で自分の手を切っちゃったんだ。それで……」
言ううちに、薄暗い電球の下であってもわかるくらい、みるみる里史の顔が青ざめていくのを見て、海里は驚く。
「父さん? どうかしたの? 平気だって、俺の血じゃないから、怪我なんかしてないよ」
「そ、そうか。ともかく海里、早くその顔を洗いなさい! 早く早く!」
里史は言って、海里の手を引っ張って洗面所へと連れていく。
優しい父親ではあるが、普段はここまで過剰に海里を心配したりしないし、過保護でもない。
不審に思いながらも、他人の血が顔についたままでは気持ち悪かったので、海里は素直に顔を洗い始めた。
「ああ、そんなに勢いよく水をかけるんじゃない! 丁寧に、そっと洗うんだ。しっかり口を閉じていろよ」
随分と細かいことを言うものだ、と海里は呆れつつタオルで顔を拭う。
「これで取れただろ?」
「……ああ。しかし、海里」
里史は、まるで今にも墓の下から死者が蘇ことを怯えているかのような、不安にかられた目をして言う。
「まさか、とは思うが。その……酔っ払いの血が、口に入ったりはしていないだろうな?」
「え? ……うん。多分」
海里は言葉を濁した。確か入ったような気もするのだが、それを言うと里史が、ひどく動揺するような気がしたからだ。
というのも、なぜか物心ついたころから海里は、絶対に他人の血を舐めたり口にしたりしてはいけない、と厳しく言われて育ったからだ。
たとえば小学校で友達が転んで怪我をしたり、指を切ったりしたときにも、間違っても消毒だからとそこを舐めたりしてはいけない。逆にバイ菌が入るから、と耳にタコができるくらい、繰り返し海里は里史に言い聞かせられたのだ。
そもそも、注意などされなくとも滅多にそんなシチュエーションには遭遇しないし、実際にこれまで一度もなかった。最近ではさすがに、里史も口にしなくなっていたのだが。
──なんでだかわからないけど、面倒くさいことになりそうだな。
海里はそう考え、男の血が口に入ったことは言わずにいることにする。けれど里史は、まだ不安を感じているようだった。