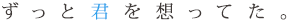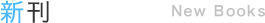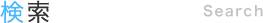高宮グループの御曹司である高宮樹にはふたつの秘密があった。
ひとつは父の実子でないこと。
もうひとつは同性愛者であること。
そのため樹は人と深く付き合うことを避けてきたが、
亡き祖父の執事である津々倉が押しかけてきてから調子が狂い始める。
愛想が悪く、しかも同居同然の津々倉に振りまわされる毎日だったが、
いつしかその気持ちは変化していく。
しかし津々倉にはある目的があって――!?
オンライン書店
電子書店
登場人物紹介
-

- 高宮樹(たかみやいつき)
高宮グループの御曹司。父の実子ではないこと、同性愛者であることを隠している。
-

- 津々倉行尋(つづくらゆきひろ)
樹の祖父の執事。主の死後、樹の執事としておしかけて来た。
試し読み
彼を見たのは、祖父の葬式の時だ。
八月の最中だが細い雨が降り続き、少し肌寒さを感じる日だった。
高宮グループの名誉会長だった祖父が死去し、大勢の弔問客が訪れる中、彼は黒い喪服に身を包み、雨の中、傘も差さずに立ち尽くしていた。
祖父の、執事だった男だ。
彼の黒い髪はしっとりと濡れ、前髪の先からぽたりと雫が頬に落ちる。それが一瞬泣いているように見えたけれど、彼はただ彫像のように黒塗りの霊柩車の方を向いているだけだった。
「樹君、そろそろ」
親戚の一人に呼ばれて樹は車に向かうが、気になってもう一度男を振り返る。彼は火葬場には来ないのだろうか。
「ああ、行くのは身内だけだからね」
親戚はそう言ったが、その執事こそ祖父の一番の身内のようなものだった。十二歳の時に祖父に引き取られた孤児で、今まで十六年間祖父のそばにいた。一年前に祖父が倒れて植物状態になったあとも、片時も離れず祖父の世話をしていたそうだ。
辺りからは、ちらほらと話し声が聞こえてくる。辛気くさい葬儀ではなかった。意識が戻らない七十八歳の老人が死んだことを誰も悲しんでなどいなかった。周囲は回復をとうに諦めていたし、樹だって、意識もなく一年も長らえたんだから、もう充分じゃないかと思っていた。
時折密やかな笑い声さえもれるこの場で、その執事は無言で主人が納められた車を見つめていた。
ただ一人、彼だけが世界が終わったような顔をしていて、それがいやに印象に残った。
それから六日後、樹はいつものように会社から歩いて帰宅し、五階建てのマンションに戻ってきた。居住している三階まで階段で上がり、自分の部屋に向かおうとした……が。
「お帰りなさいませ、樹様」
いきなり前方から声がして、樹は驚いて顔を上げた。
自分の部屋の前に黒ずくめの男がいて、斜め四十五度のお辞儀をしている。誰? と思っていると、男がすっと最敬礼から身を起こした。
すらりと背の高い男だった。